通貨とは?
通貨とは、「流通貨幣」の略称の事を指し、決済のための価値交換媒体とも言えます。
通貨は、政府が発行する貨幣と中央銀行が発行する銀行券の総称であり、発行する国家などの信用によって価格が変わります。なので、国の財政破綻や信用が失墜する事によって、通貨の価値が無くなって紙切れになると言うこともあり得なくない話なのです。
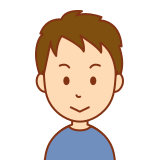
通貨が信用で成り立っている証ですね
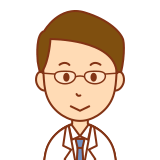
そうですね。
紙幣は「日本銀行」が、硬貨は「政府」が発行しています。
それを私たちが信用しているからこそ貨幣経済は成り立ちます。
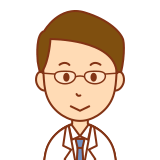
ちなみに、
仮想通貨が信用される理由は「ブロックチェーン(過去に行われた全ての取引データをブロックにまとめた分散型のデータベース)」があり、
この事により中央管理者が不在になりトラストレス(第三者を信用する必要がない)が可能となるのです。
そして、通貨はUSD(米ドル)やJPY(日本円)のようにアルファベット3文字で示すことができ、この表し方が金融世界で標準的となります。
この表し方を「通貨コード」言い、ISO4217という国際的な基準で決められていますので、次の項目で通貨コードの見方を覚えましょう。
通貨コードの見方 〜2文字・1文字のルール〜
まずは通貨コードのアルファベットについて説明します。
3文字のうち「左の2文字が国名」を表し、「最後の文字は通貨の名称」を表しています。

基本的にはこの仕組みなのですが、一部で例外もあります。
ユーロは国ではなく経済協力圏で使われる通貨のため左の2文字はヨーロッパ全体を表しています。
本来なら通貨のユーロのスペルは「Euro」と書くので、「2文字・1文字ルール」に従うなら「EU・E」と書きそうなものですが、ユーロの場合は最後の文字を省いた「EUR」が使われます。
例えば、メキシコの通貨を見てみましょう。
メキシコの通貨名称は「ペソ(Peso)」ですが通貨コードは「MXN」と書きます。
なぜ、通貨の名称がPなのにNから始まるのか説明しますと、メキシコの通貨は1回だけ1/1000のデノミネーションが行われ「旧ペソ」から「新ペソ」へと変わりました。新ペソは「Nuevo Peso」と書くことができ、これによって通貨コードが「MXN」になりました。
その後、通貨名称は「新ペソ(Nuevo Peso)」から「ペソ(Peso)」に戻されましたが、通貨コードは新ペソ時に与えられたままだったので、「MXN」のままなのです。
その通貨単位を切り下げる(金額の桁数表示を小さくする)、または切り上げる(金額の桁数表示を大きくする)こと。デノミとも略される事もある。
経済政策の1つで、急激なインフレやデフレが起き、経済活動に支障をきたす際の解決手段として行われる。また、新たな為替相場制度への変更や通貨同盟への参加等の際に実施される。
とくに、ハイパーインフレ時(通貨の価値(信用度)が著しく低下し物価が大幅に上昇する事であり、国際会計基準によると「3年間で累積100%以上の物価上昇」の状態)に切り下げとともに、旧通貨から新通貨に切り替えるケースが多く、デノミ以前に使用できた旧通貨の単位が強制的に切り捨てられることで、市場における通貨量が減少し需給の関係が調整されると、ハイパーインフレがなくなると考えられる。
なお、デノミそのものによる他通貨との交換レートへの影響はない。
このように、「2文字・1文字ルール」が通じないものが多々あります。
この通貨コードを2つ並べると、FXでお馴染みの通貨ペアになるという訳です。
FXで見られる通貨コードの一覧表です。
| 国名・地域名 | 通貨名 | 通貨コード |
|---|---|---|
| EU圏 | ユーロ | EUR |
| イギリス | ポンド | GBP |
| オーストラリア | オーストラリアドル | AUD |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZD |
| アメリカ | アメリカドル | USD |
| カナダ | カナダドル | CAD |
| シンガポール | シンガポールドル | SGD |
| スイス | スイスフラン | SHF |
| ノルウェー | ノルウェークローネ | NOK |
| スウェーデン | スウェーデンクローナ | SEK |
| 中国 | 人民元 | CHN |
| 香港 | 香港ドル | HKD |
| 南アフリカ | 南アフリカランド | ZAR |
| トルコ | トルコリラ | TRY |
| メキシコ | メキシコペソ | MXN |
| 日本 | 日本円 | JPY |
通貨の大まかな種類分け
通貨には多くの種類があり、今回は「主要通貨」、「基軸通貨」、 「資源国通貨」と「高金利通貨」の3種類の通貨を紹介します。
1. 主要通貨
主要通貨と言われる通貨は、主に先進国の通貨の事を指し実需筋や投機筋にも多く取引される通貨。
どの通貨までを主要通貨というかは、どう定義するかでも異なります。
FXでは通貨の取引量が多い通貨が主要通貨の場合があります。
USD(米ドル)、EUR(ユーロ)、JPY(日本円)、GBP(英ポンド)、豪ドル(AUD)
※基本はUSDが基軸通貨とされる。基軸通貨の説明は、下記で行なっているので参照してください。
※左から取引量が多い順に並んでいる。出典は、BIS(国際決済銀行)の2016年から2019年のデータから。
【通貨ごとの取引シェア:2016-2019年】

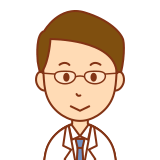
主要通貨の見方は、使う場面や人によって定義が違う可能性があります。ニュースの報道とかだと下記の内容でも使うことがあります。それぞれの場面で主要通貨の定義をしっかり確認しましょう。
・IMF(国際通貨基金)のSDR(特別引出権)で採用されている通貨でいうなら、
USD(米ドル)、EUR(ユーロ)、CHN(人民元)、JPY(日本円)、GBP(英ポンド)などが上げられる。
少し特殊な言葉が出たので、下記に記しておきます。
わからない単語があったら、ここから見てね。
IMFは、1944年にブレトン・ウッズ会議(米国ニュー・ハンプシャー州ブレトン・ウッズで開催された連合国国際通貨金融会議)で創立が決まり、この会議で調印された「IMF協定」により1947年に業務を開始した国際機関の事。2020年10月頃の加盟国は190か国です。
IMFの主な目的は、
①加盟国のサーベイランス(為替政策の監視)
②国際収支が著しく悪化した加盟国に対して融資などを行って、以下の事に寄与すること。
(1)国際貿易の促進
(2)加盟国の高水準の雇用とGNI(国民所得)の増加
(3)為替の安定
IMFが1969年に創設した国際準備資産のことであり、融資を行う時の単位である。IMF加盟国は出資割合に応じて融資を受ける権利が割り当てられており、国際収支が悪化した場合には自国が持つSDRを他の加盟国に渡すことで外貨を手に入れることができる仕組み。
BISは、1930年に設立された中央銀行をメンバーとする組織で、スイスのバーゼルに本部が置かれている。2021年6月末頃、日本を含め63か国・地域の中央銀行が加盟してる。日本は1994年以降、理事会のメンバーになっている。
ドイツの第1次大戦賠償支払に関する事務を取り扱っていたことが行名の由来ですが、それ以外にも、以下の事を行っている。
①中央銀行間の協力促進のための場の提供
②中央銀行からの預金の受入れ等の銀行業務
公式サイト
https://www.bis.org/
2. 基軸通貨
基軸通貨とは、先程あげた主要通貨の中でも更に中心的な地位を占める通貨の事を指します。現在だとUSD(米ドル)です。
基軸通貨になる為には、3つの条件を満たしている必要があります。
-1. 各国通貨の価値基準となる
-2. 各国の銀行等が対外準備資産として保有する通貨(外貨準備)であること
-3. 決済通貨であること
3. 資源国通貨
資源国通貨とは、資源の輸出への経済的依存度が高い国の通貨の事を言う。
鉄鉱石や石炭の資源の輸出が多い。どちらも輸出量では世界1位。日本、中華人民共和国、韓国、インド、アメリカ合衆国が大手輸出相手国である。
原油や天然ガスなどの資源の輸出が活発です。石油輸出量・天然ガス輸出量が世界で5位 。
世界全体の生乳生産量の3%程度であるものの、国内の人口が480万人と少ないく国内で生産された牛乳・乳製品の95%を輸出している事から、主要な乳製品輸出国となっている。
南アフリカが金やパラジウムなどの鉱山資源の輸出が活発。
資源国通貨は、その国が輸出する資源の価格の影響を強く受けるという特徴がある。
例えば、原油価格が上昇すると、カナダドルは買われ、逆に原油価格が下落するとカナダドルが売られる傾向などがある。
4. 高金利通貨
高金利通貨とは、政策金利(中央銀行が金融政策の手段として操作する金利)など金利水準が高い国の通貨を指します。
オーストラリア(豪ドル『AUD』)、ニュージーランド(ニュージーランドドル『NZD』)
メキシコ(メキシコペソ『MXN』)、トルコ(トルコリラ『TRY』)、南アフリカ共和国(南アフリカランド『ZAR』)
今回は日本と比べて金利が高いか低いかを比較している。
「高金利」の認識は、国によって異なる。低金利である日本からみると他の多くの国の通貨は高金利になりますが、一般的には、上記の国が挙げられる。
高金利通貨は高い利回りの恩恵を受けることができるが、政治・経済基盤の脆弱性によるリスクも抱えている点に注意を要します。
またマイナス材料が発生すると、その国の株・債券・為替相場などのボラティリティ―(価格変動性)が大きくなりやすい特徴があります。
- 地政学的なリスク
- 経済成長率の低迷
- 市場の不完全性
- 高インフレ
- 比較的高水準の経常赤字および対外債務
- 政治的な不透明性・不安定性
などが挙げられ、これらが金利や為替相場等の急激な変動につながる可能性があります。

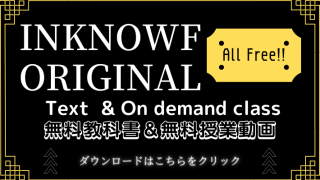
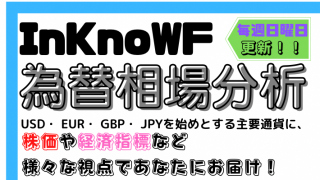
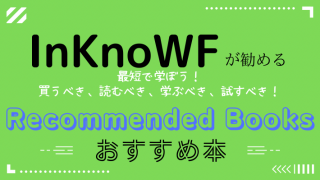


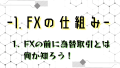
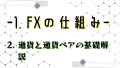

コメント