為替とは?
まず、為替とは、振込や送金、手形や小切手を使用することで、現金を移動させずに代金の支払い等の決済を行うことを指します。そして、為替は「内国為替」と「外国為替」に分けられます。
内国為替とは?
簡潔にいうと、その通貨の国内において金融機関を通じてその国内の通貨で送金する事を指します。
一般的には、国内にいる債権者や債務者に銀行間の口座振替を使って取立てや送金を行う資金決済の仕組みの事を指します。

外国為替とは?
簡潔にいうと、異なる通貨の交換を行うことを指します。
一般的には、国ごとで通貨が異なる国際間の貸借関係を、現金で直接輸送することはなく信用手段(為替手形や送金小切手など)によって決済されます。
FXは、こちらの仕組みを利用した取引になります。

外国為替市場の取引参加者
外国為替は、世界中の外国為替市場で同じ通貨が取引されているため、取引の流動性が高く、さまざまな市場参加者が多様な取引を行なっています。
ちなみに、ニュース等で目にすることがある為替レートは「直物市場」のスポットレートであり、対顧客市場の為替レートには、そこに手数料が追加されます。

おまけ -日本の為替の歴史-
ちなみに、為替という言葉が誕生したのは鎌倉時代であり、「交わす」(交換する)の連用形「かわし」が変化したものが「かわせ」になります。
この時代の為替は、金銭のみならず米やその他の物品の授受にも用いられていました。
そして、時を遡ること江戸時代。
江戸時代では、主に金銭をメインとした為替取引が大きく発展したとされています。まず、多額の金銭を持って「政治・消費都市の江戸」と「経済的中心の大阪」を行き交うのはとてもリスクがありました。
その為、下記の図の仕組みを行うことででリスクを回避しており、支払手段としての貨幣機能の発展・信用取引の発展を促し、最終的には両替商あるいは大都市それぞれに店舗を持つ大商人を仲介とした為替取引を発達させ流ことになりました。

言葉で表すと下記のようになります。
※実際には、「為替手形」以外にも「置手形」があるが簡略するために省略している。
- ①「江戸の商人」が「江戸の両替商」に100両を預ける。
- ②「江戸の両替商」は、「江戸の商人」に『為替手形』を作成して「江戸の商人」に渡す。
- ③「江戸の商人」は、『為替手形』を「大阪の商人」に渡す。
- ④「大阪の商人」は、『為替手形』を「大阪の両替商(「江戸の両替商」によって指定された両替商)」に為替手形を渡す。
- ⑤「大阪の両替商」から100両を受け取る。

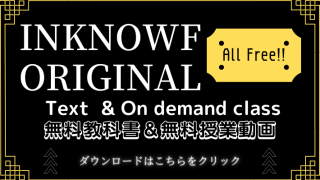
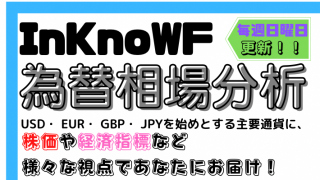
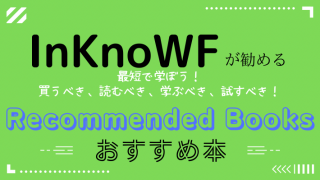


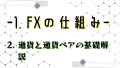

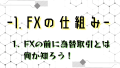
コメント